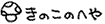2014/11/23�����ˡ�
�����˥��å�, D. W. (1971/1987)�Ҥɤ�μ������̭��������ؽѽ��Ǽ�
|
| �����˥��åȤλҤɤ�����ܤλ��㽸�Ȥ���������������֥��𤷤ơ������ɤ������餫�ˤʤäƤ����Τ���ʬ���äƤ��롣�����ˤ⤢���̤ꡢ�������ä���Ƥ��뤳�ȤϤ���������ꤵ�줿���Ź�¤�Τʤ��ǡ�1��1�Ǥʤ���Ƥ������ꥢ��ʹ�����������Ƥ����������Ȼפ��������Ƥޤ�������ε��Ҥ����ݤϡ��ɤ꤬�ڤ�����ɤळ�Ȥ��Ǥ��뤫�ݤ��ˤ��롢�Ȥ����Ȥ����ˤ�����ȴ�ò�� | | |